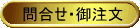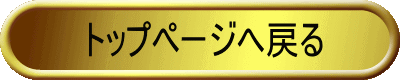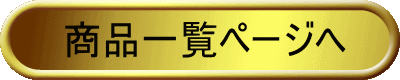A-3.弁財天曼荼羅 売約済
面相の墨線は残っています。
サイズ 本紙 縦997㎜、横370㎜、表具 縦1980㎜、横370㎜ ※軸端を含まず
絹本著色、軸装、室町時代中~後期(16世紀)
八臂弁財天を中尊として曼荼羅状に諸尊が並んだ「弁財天曼荼羅」です。
密教の別尊曼荼羅とも垂迹曼荼羅とも別系統の曼荼羅で、様々な尊格が複雑に習合した中世独特の信仰を具現化した曼荼羅と思われます。
尊像の配置は中央に八臂弁財天、その上に三光天子、中尊の下には十五童子と二人の稚児、荷車、牛、馬が描かれています。
上部の三光天子は中央に明星天子(星)、日天子(日天=太陽)、月天子(月天=月)の並びです。
尚、明星天子は虚空蔵菩薩の化身とも言われ、ここでは剣と宝珠を持った虚空蔵菩薩の姿で描かれています。
作りは室町時代特有の目の粗い絹本に細密な描写がされています。
顔料は発色が控えめで截金こそありませんが、配色のバランスもよく時代の古色も相まって趣を増しています。
保存状態は室町時代特有の絹本に描かれているため、顔料の定着悪く胡粉の剥落が目立ちます。
特に中尊の胡粉の剥落が目立ちますが、顔立ちの墨線は残っています。また、色の抜けは少なく、補筆はありません。
本紙は修理の手が入り、折れ、シワはありません。
表具は古裂で仕立てられ、金茶の亀甲文の金襴(銀襴に近い鈍い光沢)と、緑色の上下の合わせで、傷みは殆どありません。
軸端は鍍金の彫金金具、古い桐箱入りです。表具の状態の良さはこの作品の特筆すべき点です。
弁財天と十五童子を並べた図柄の作例は多数ありますが、三光天子の加わった作例は未だ見たことがなく、図録でも見た記憶はありません。
密教の曼荼羅とも垂迹曼荼羅とも異なる中世独特の混沌とした信仰を表す貴重な資料です。